※この記事はプロモーションを含みます
※本ページは、アフィリエイト広告を利用しています
従業員から家族の不幸の連絡があったとき、総務担当者としてどのように対応すればよいか・・・いざ、その場面になったら戸惑うことがありますよね。

私も総務なりたての頃は、訃報関係のマニュアルもなかったし、スムーズに対応できませんでした・・・
失礼があったら大変なので、訃報対応は本当に気を張ります。。
今回は、中小企業の総務担当者の私が、実際に社員の忌引があった際に対応した流れ5つのステップを紹介します。
この記事でわかること
- 従業員からの訃報連絡を受けた際の初動で確認すべきポイント
- 社内への適切な周知方法とメール文例
- 会社としてのお悔やみ(香典、弔電、供花)の準備と手配
- 従業員への忌引や有給休暇などのサポート、証明書の扱い
初動確認:状況を把握する

私が総務担当者として、とある部署の方から訃報の連絡が来た際には、まずは冷静に、以下のポイントを押さえ、状況を確認しました。
- 故人との関係性
祖父母、両親、兄弟、配偶者、子など、具体的な関係を把握 - 葬儀の日時・場所・喪主名
葬儀の準備が進んでいる中で確認するため、メールやショートメッセージでの連絡をおすすめします。 - 従業員が必要としているサポート
何日ほどお休みする予定か、業務の引き継ぎ有無などを確認 - その他の連絡事項
家族葬の場合の香典辞退や社内での訃報連絡についての希望確認
※両親、配偶者、子の場合であれば、弔電、供花をする会社が多いです。その場合は、必ず喪主を聞くようにしましょう。
訃報があった際は、葬儀の手配などでバタバタしていることが多いです。
電話だと聞き間違えなどがあるので・・・、特に故人や喪主の名前を間違えないよう、できればメールやショートメッセージなどでもらうと良いかもしれません。
社内への周知(メール例あり)

訃報を受けた後、社内への周知も重要です。ただし、プライバシーには細心の注意を払いましょう。
私の場合、以下のように進めました。
- メールや社内掲示板(私の会社ではLINE WORKS)にて周知
周知の範囲ですが、私の会社では全社員ではなく、管理者(各箇所長)までとし、対象の社員の部署のみ箇所長からメンバーに周知してもらうというやり方を取っていました。

あらかじめ周知範囲を決めておくと良いですよ♪
社内周知の際ですが、情報の伝え方に注意し、丁寧な表現を心がけ、案内文は次のように出していました。
件名:【訃報】営業部 A社員ご母堂ご逝去の報
本文:
営業部 A社員のご母堂さま(⚫︎歳)におかれましては、病気療養中のところ薬石効なく、2025年⚫︎月⚫︎日のご逝去されました。ここに謹んでお知らせいたします。
記
1.通 夜 2025年⚫︎月⚫︎日 18時より
2.告別式 2025年⚫︎月⚫︎日 11時より
3.場 所 ⚫︎⚫︎⚫︎葬儀場 (住所&電話番号)
4.喪 主 ⚫︎⚫︎⚫︎氏(故人との関係:(例)長男)
5.その他 家族葬につき、弔電、供花等につきましては、ご遺族のご意向によりご辞退申し上げます。
以上

周知の文例は、コピーして使用してもよいですよ♪
周知は、周囲の理解を深め、サポートの輪を広げるための大切なステップです。
お悔やみの準備

お悔やみの方法は多様ですが、企業文化や従業員の希望に応じた対応が求められます。
私の会社では、弔電と供花対応するのは、1等身までとして、次のように進めました。
香典の手配
私の会社では、配偶者:5万、両親・子:2万と慶弔規定で定めていました。
また、会社の代表者は社員の葬儀には弔問しないとしていたので、(対応できなかった場合に不公平感が出るので)、香典は後日出社した際に本人へ渡していました。
弔電・供花の手配
供花は一般的に葬儀場に問い合わせし、手配することが多いのですが、毎度大変なので、ネットで注文できる佐川ヒューモニーのVERY CARDを利用していました。
葬儀場によって指定がある場合、佐川ヒューモニーが代わって対応してくれるので、とても便利なサービスです。法人版であれば請求書対応も可能なので、経費処理もバッチリです。

VERY CARDなら、当日の対応も可能です!
時間に間に合わない時は、自動的にNTT代行でやってくれます☆
VeryCardは、簡単にオンラインでお悔やみ電報を送ることができるサービスです。弔電とあわせて供花も届けられるので、ぜひ活用してみてください。
従業員へのサポート(有給休暇や忌引の処理)

訃報でお休みされる際は、有給休暇にする場合もあると思いますが、独自で忌引を設定している会社もあると思いますので、自社の規程に基づいて処理しましょう。
私の会社の場合、忌引(有給)で処理していましたので、忌引の証明を提出いただいてました。
忌引の証明とは・・・・
死亡診断書、埋葬許可証・火葬許可証、葬儀証明書、葬儀案内はがきなどが挙げられます。
私の会社では、葬儀の案内はがきを出す人が多かったです!
まとめ
訃報への対応は、総務担当者にとって重要な役割です。従業員への配慮を忘れず、適切なサポートを行うことで、信頼関係を築くことができます。
本記事を参考にぜひ慌てずに対応してください。心のこもった対応が、従業員の安心感につながりますよ♪
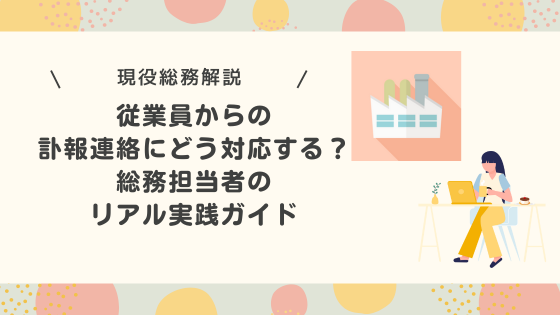
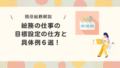
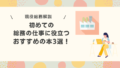
コメント