※この記事はプロモーションを含みます
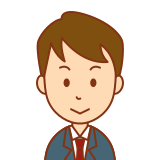
担当者A男
SmartHRってよく聞くけど、本当にウチみたいな中小企業で効果あるの?
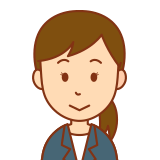
紙の書類だらけで、毎月の給与計算や入社手続きがアナログすぎて辛い…
総務人事の仕事って、気づけば「書類に追われる毎日」になりがちですよね。
私の職場も例外ではなく、給与計算や入社手続きのたびに紙の束と格闘し、配布や回収だけで半日がつぶれることも…。
そんな状況を変えてくれたのがSmartHRでした。
導入後は業務が効率化しただけでなく、「従業員と会社の関係が良くなる」という思いがけない変化もあったんです。
しかし、それは単に「楽になった」という話ではなく、会社と従業員の関係性を良くする変化のきっかけになったのです。
この記事では、私が実際に体験したSmartHR導入後のリアルな変化と、導入前に知っておきたかった注意点を本音で語ります。
- SmartHR導入による具体的な業務時間の削減効果
- ペーパーレス化がもたらす効率化以外のメリット
- 従業員満足度が向上した具体的な活用方法
- 導入を成功させるために注意すべきポイント
SmartHRで業務改善!ペーパーレス化がもたらした3つの効果

SmartHR導入の最大のメリットは、何と言ってもペーパーレス化です。
当たり前にやっていた紙業務がなくなることで、時間だけでなく、精神的な負担も大幅に軽減されました。
ここでは、特に効果が大きかった3つの業務改善についてお話しします。
【効果1】入社手続き・雇用契約の手間とコストを8割削減
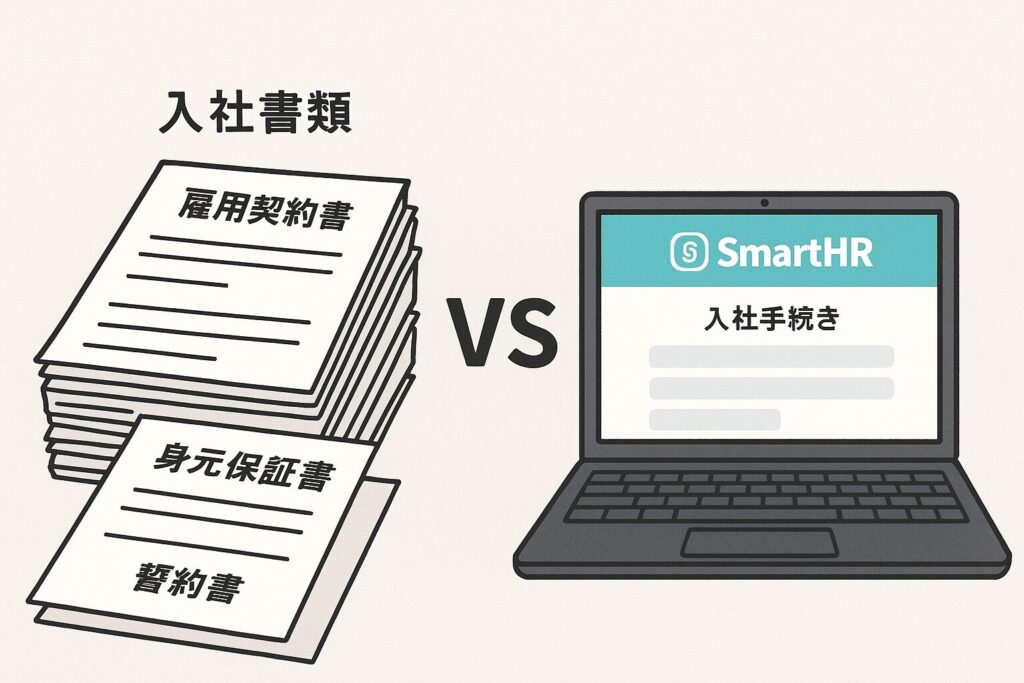
以前は、新しい従業員が入社するたびに、大量の書類を印刷して郵送し、返送を待つという手間がありました。
記入漏れやハンコの押し忘れがあれば、電話で連絡して再送してもらう…なんてことも日常茶飯事。
1人あたり最低でも1週間はかかっていました。
SmartHRを使うと、郵送の待ち時間がなくなり、入社手続きが最短その日のうちに完了できるようになりました。
以前は「印刷→郵送→返送→チェック」で最低1週間はかかっていたので、この差は本当に大きいです。
書類の準備、郵送代、保管スペースといった物理的なコストもゼロに。
従業員もスマホから簡単に入力できるので、入社初日からスムーズに業務に集中してもらえるようになりました。

あの頃の苦労を考えると、本当に楽になりました。紙がなくなったのは大きいです!!
SmartHRで創出できた時間で、新入社員との面談やフォロー、社内イベントの企画に時間を割けるようになり、定着率向上という副次的な効果にも繋がっています。
【効果2】問い合わせ9割減!面倒な年末調整からの解放

総務人事の皆さんなら共感してくれると思いますが、年末調整は一年で最も憂鬱な業務の一つですよね。
社員全員の申告書を配って、回収して、一枚一枚チェックして、不備があれば本人に確認して…。
毎年、この時期は問い合わせの電話が鳴りやまず、他の業務が完全にストップしていました。
SmartHRの年末調整機能は、まさに救世主でした。
従業員がアンケート形式で質問に答えていくだけで、申告書が自動で作成されます。
保険料控除の証明書もスマホで撮影してアップロードするだけ。

記入例の案内を何度もする手間がなくなりました!
控除といった意外にわからない言葉の意味も、SmartHRのやさしい日本語の機能で、わかりやすく表現してくれるので、よく聞かれる質問もグッと減りました!
システムが入力内容を自動でチェックしてくれるため、明らかな記入ミスや計算間違いがなくなり、私たち担当者への問い合わせ件数は導入前の1割以下に。
おかげで、年末の繁忙期でも定時で帰れる日が増え、精神的な平穏を手に入れました。
【効果3】従業員情報の一元管理で「あの書類どこ?」がゼロに
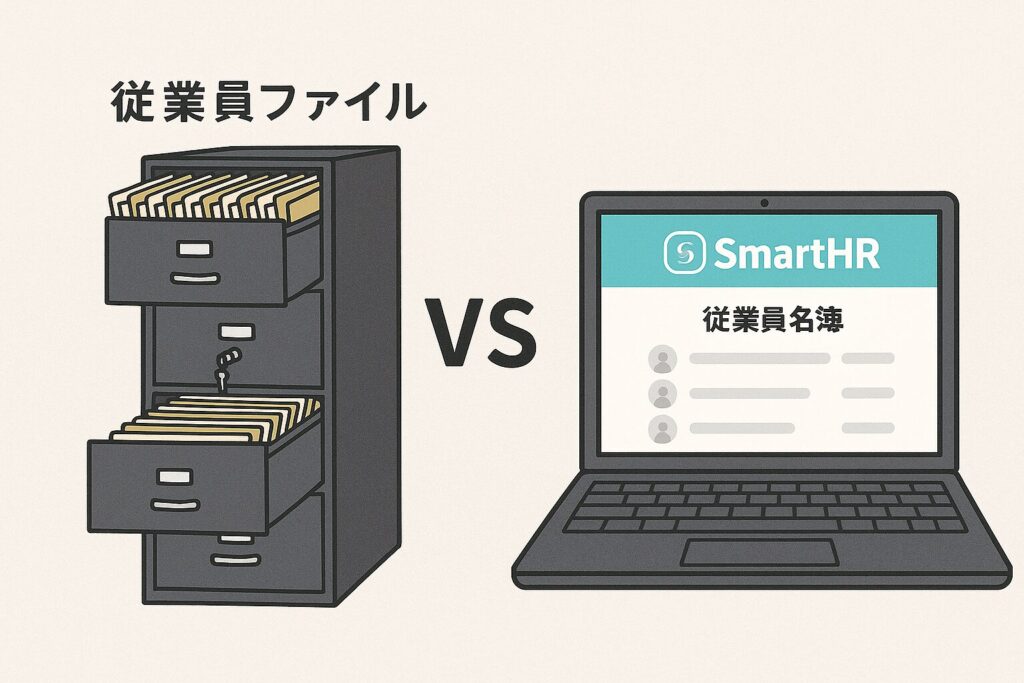
あの人の住所変更の書類、どこにしまったっけ…
この人の扶養家族の情報をすぐに確認したい!
以前は、従業員情報を探すためだけに、キャビネットの前で多くの時間を費やしていました。
紙の履歴書、雇用契約書、住民票などがファイルごとにバラバラに保管され、最新の情報がどれか分からなくなることも。
SmartHRは、これらの従業員情報をすべてクラウド上で一元管理できます。
従業員自身が住所変更や家族情報の更新をスマホから申請できるため、情報は常に最新の状態に保たれるのです。
何か情報を確認したい時も、名前で検索すれば一瞬でアクセス可能。

法改正に伴う情報更新も一括で対応できて助かります。
これにより、書類を探すという時間は完全になくなりました。
情報漏洩のリスクも、鍵付きキャビネットより格段にセキュリティの高いクラウドで管理する方が安全だと感じています。
従業員満足度を高めるSmartHR活用法3選

SmartHRを導入して気づいたのは、単なる業務効率化ツールではないということです。
使い方次第で、従業員とのコミュニケーションを円滑にし、会社への信頼感や満足度(従業員エンゲージメント)を高める強力な武器になります。
ここでは、我が社で実践している活用術を3つ紹介します。
【活用法1】Web給与明細|「紙で欲しい」の声がゼロになった方法
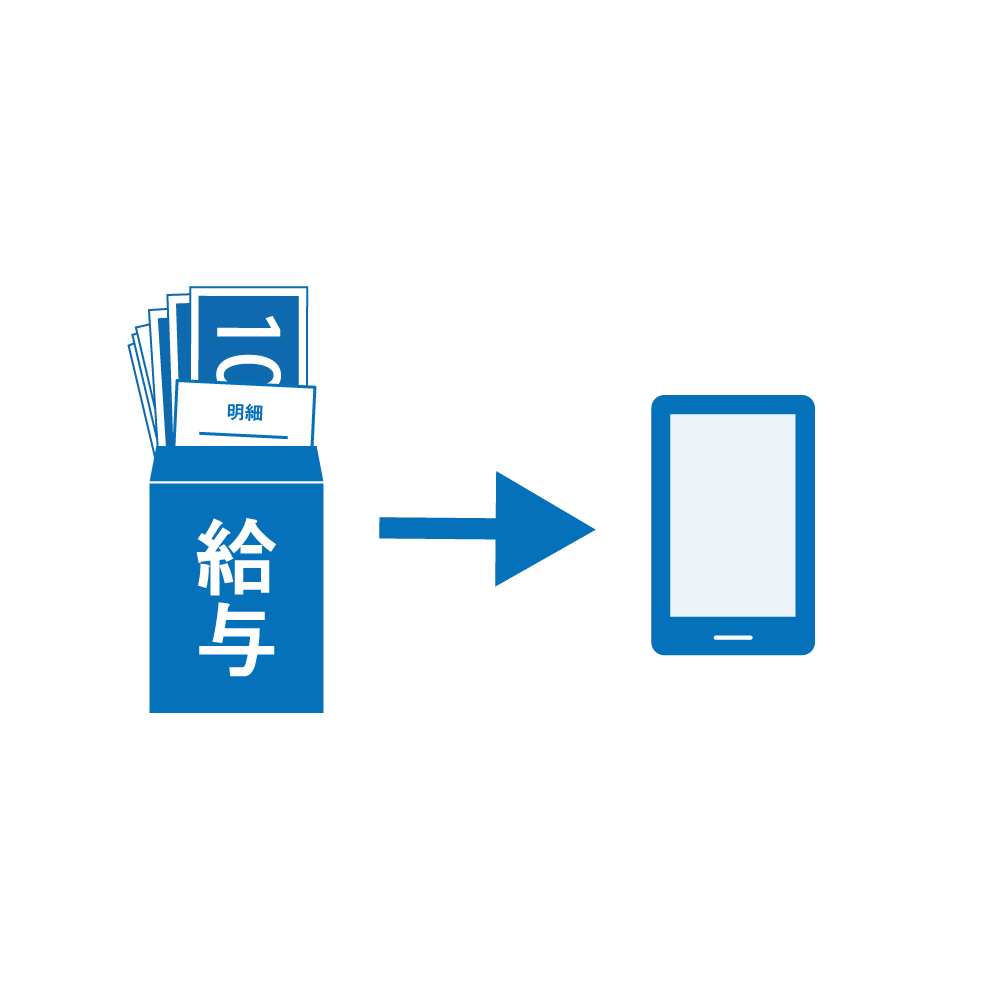
給与明細の電子化は、今や多くの企業で進んでいますが、中小の製造業である当社では「PCやスマホが苦手な人も多いから無理だろう」と諦めていました。
導入当初は、案の定「紙で欲しい」という声も一部から上がりました。
しかし、SmartHRはスマホアプリの操作性が非常に高く、誰でも直感的に使えるデザインになっています。
導入時に丁寧な説明会を開き、個別にフォローする体制を整えた結果、3ヶ月後には「紙で」という要望はほとんどなくなりました。
むしろ、「いつでもスマホで確認できて便利」「過去の明細もすぐに見返せるのが良い」と好意的な声が多数派に。
印刷、封入、配布という毎月の面倒な作業から解放されたのはもちろん、従業員一人ひとりのITリテラシー向上にも繋がり、会社全体のデジタル化を推進するきっかけにもなりました。
【活用法2】従業員サーベイ|匿名だからこそ見える現場の本音

【表:簡単な従業員サーベイのアンケート項目例】
| カテゴリ | 質問項目例 |
|---|---|
| 仕事のやりがい | 現在の仕事にやりがいを感じていますか? |
| 人間関係 | 上司や同僚とのコミュニケーションは円滑ですか? |
| 職場環境 | 職場の環境(明るさ、清潔さ等)に満足していますか? |
| 会社への期待 | 会社に今後どのようなことを期待しますか?(自由記述) |
これまで、従業員が会社に対してどう思っているのか、本当のところは分かりませんでした。
年に一度の面談では、どうしても建前論になりがちです。
そこで活用したのが、SmartHRの従業員サーベイ機能です。匿名でアンケートを実施できるため、従業員も本音を書きやすいのが特徴です!
サーベイを実施してみて驚いたのは、想像以上に「リアルな声」が集まったことです。
たとえば「特定部署の残業が多すぎる」「休憩室の椅子が古くて腰が痛い」といった、普段の会話では出てこないような意見が続々と出てきました…。
小さな改善点でも、従業員からすれば「会社が自分たちを見てくれている」と感じてもらえる効果がありました。

サーベイ結果は経営層への客観的な報告資料になります!
これらの声をもとに職場環境の改善を進めたことで、従業員から「自分たちの声が会社に届いている」という信頼感を得ることができました。
これは、単なる業務効率化では得られない、非常に大きな価値だと感じています。
【活用法3】お知らせ機能の活用で、社内コミュニケーションを活性化
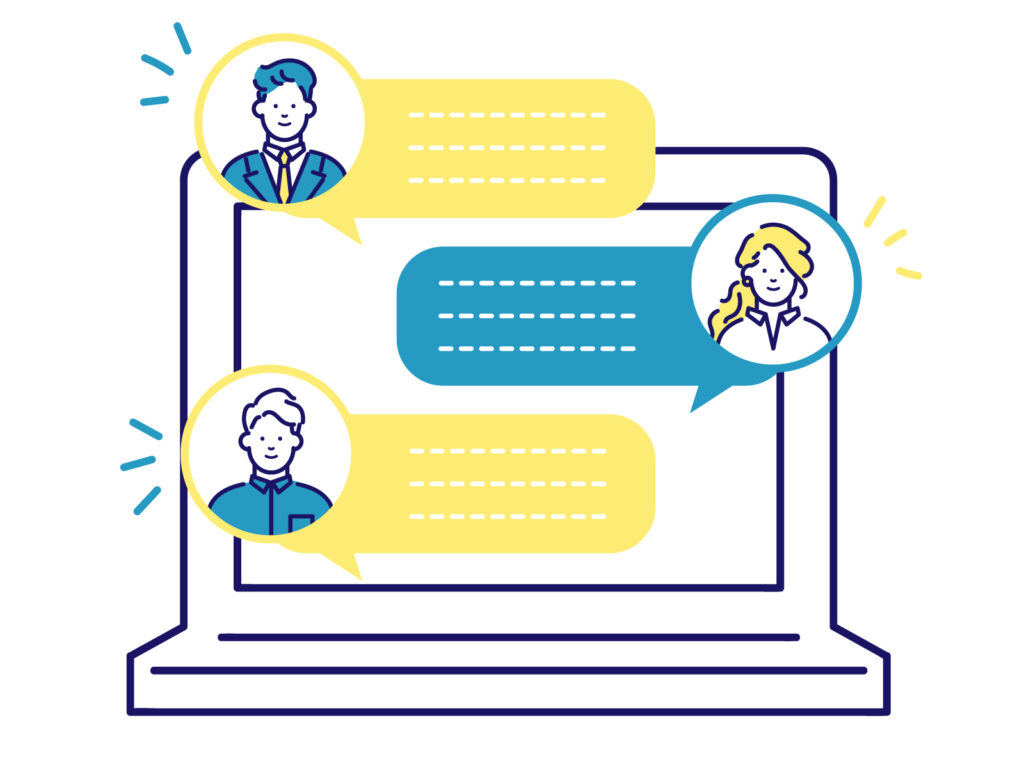
SmartHRには、お知らせを全従業員に一斉配信できる機能があります。
我が社ではこれを「社内ポータル」として活用しています。
慶弔連絡や社内規定の変更といった公式な連絡はもちろん、新しい仲間が入社した際の自己紹介や、部活動の活動報告、社長からのメッセージなどを定期的に発信。
製造現場で働く従業員は、普段なかなか社内全体の動きが見えにくいのですが、スマホから手軽に会社の「お知らせ」を知れるようになりました。

特に、現場の社員は係長を通じて連絡をしていたのですが、それに加えてSmart HRのお知らせ機能を使って、リアルタイムで通知できるようになりました!
また、社内報もお知らせ機能を使って届けることで、社員分の印刷をすることなく、届けることができるようになりました。(紙を希望する方には、人数分紙を印刷しています)
こうした小さな積み重ねが、組織の一体感を醸成し、働きやすい雰囲気作りに繋がっていると実感しています。
【導入前に必読】SmartHRで失敗しないための2つのポイント
-1024x724.jpg)
ここまで良いことばかりを書いてきましたが、もちろん導入が順風満帆だったわけではありません。
どんなに優れたツールでも、使い方を間違えれば宝の持ち腐れです。
これから導入を検討している方々が同じ失敗をしないよう、私たちが実際に直面した注意点と、その対策を共有します。
【注意点1】「使えない…」を防ぐ、ITが苦手な従業員へのフォロー術
-1024x768.jpg)
私たちの会社もそうですが、製造業にはPCやスマホの操作に不慣れな従業員が少なくありません。
ただ「システムを導入しました、各自で設定してください」と丸投げするだけでは、必ず反発が起こり、活用されずに終わってしまいます。
導入を成功させる鍵は、いかに丁寧なフォローができるかにかかっています。
私の会社では、全従業員を対象とした説明会を複数回開催し、その場で全員に初期設定を完了してもらうようにしました。
また、各部署にITが得意な若手社員を「SmartHR推進リーダー」として任命し、分からないことがあればすぐに聞ける体制を構築。

最初は大変ですが、導入初期の丁寧な説明会が後の運用を格段に楽にします!
私の場合、説明会の時点で、「この人はもう少し個別にサポートが必要だな・・・」などがわかったので、アフターフォローも入れつつ、進めました。
最初は「面倒だ」と言っていたベテラン社員も、一度便利な機能を体験すると、すぐに慣れてくれました。
導入担当者の負担は一時的に増えますが、この初期段階での丁寧なコミュニケーションが、後のスムーズな運用に不可欠です。
【注意点2】初期設定とデータ移行の壁。自社だけで抱え込まない
| 設定項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 就業規則 | 会社のルールに合わせて各種設定を行う | 労働基準法との整合性を要確認 |
| 従業員情報移行 | 既存の従業員データをCSV等でインポートする | データのクレンジングが重要 |
| 給与情報設定 | 給与体系や手当、控除項目を設定する | 社労士など専門家への確認が推奨される |
| 各種連携設定 | 勤怠管理や給与計算ソフトと連携させる | API連携の仕様を事前に確認 |
SmartHRは非常に多機能な分、初期設定にはある程度の知識と時間が必要です。
特に、これまで紙やExcelで管理してきた従業員データをシステムに移行する作業は、想像以上に骨が折れます。
データの表記揺れを修正したり、不足している情報を補ったりと、地道な作業が続きます。
正直なところ、私たちも自社の人員だけでは手が回らず、SmartHRが提供している導入サポート(有償)を利用しました。
専門の担当者が、就業規則に合わせた設定の相談に乗ってくれたり、データ移行の具体的な手順を教えてくれたりしたおかげで、スムーズに導入準備を進めることができました。

私は最初に全て1人で進めようとしましたが、心が折れました(泣)
社労士さんや経理担当者の方にもお願いして、移行作業を進めました。
導入コストはかかりますが、自社のリソースだけで抱え込まず、外部の力をうまく活用することも、プロジェクトを成功させる重要なポイントだと学びました。
【まとめ】SmartHRは第二の事務員として迎え入れるのも有
Smart HRを第2の事務員として迎え入れることで、100人規模の製造業の当社で「どのように業務が変わり、何を得られたのか」を実体験ベースでお話ししました。
入社手続きや年末調整といった定型業務にかかる時間が劇的に削減されたのはもちろんですが、それ以上に大きな収穫だったのは、Smart HRによって空いた時間を「人にしかできない仕事」に使えるようになったことです。
SmartHRの導入で、総務人事の仕事は劇的に変わり、単なる効率化だけでなく、社内のコミュニケーションが円滑になったので、導入して本当に良かったと思っています。
もし今、
- 書類や年末調整に追われて毎日バタバタしている
- 人事データがあちこちに分散していて探すのに時間がかかる
- 「働きやすい会社」にしたいけど、何から始めればいいかわからない
こんな悩みをお持ちなら、まずはSmartHRを試してみるのがおすすめです。
無料トライアルもあるので、実際に触ってみると、「これまでの苦労は何だったのか…」と感じると思いますよ。
SmartHRは、人事労務の仕事を「作業」から、従業員と向き合い、より良い組織を創る「戦略的な仕事」へと進化させるきっかけをくれました。
日々の煩雑な業務に追われ、本来やるべき仕事に手を出せずにいるのであれば、SmartHRで業務効率化をしてみてはいかがでしょうか。
中小の総務人事の私が実感した3つの効果と注意点.jpg)


コメント